「彼らは、最初にまず目的地を決めると、
そのからあとはずっとその目的地に向かって進むというやり方をしないんだ。
進行方向に向けて、最初にこのポイントでこの角度に進路を変更して、
それから、次のポイントで、この角度に進路を変更して・・・・
というようにして進んで行くんだ。
(参考; Go / No Go ディシジョン)
だから、たとえ最終的に到着した場所が最初の目的地と違っていても、
その当事者たちは、
『われわれは正しかった。なぜならその時々で、正しいと思える判断がなされて来たのだから、
到着地が最初の目的地と違っていても、それが目的地になって良いのだ。』
というような主張をする。」
「・・・・・?」
「例えば、英国から日本に向けて出発するとする。
彼らは、まず大西洋に出て、進路を変え、それから喜望峰に行って、それから再び進路を変更して、
というようにやって行った結果、日本に行くはずが、なぜかインドに到着したとする。
それでも、途中の判断があっているから目的地がインドになっていていいんだ、っていうこと。
それが英国人の『プラグマティズム』というやつだ。」
このたとえ話は、いわゆるプロジェクト・マネジメントでいう「プロジェクト・スコープがだんだん変わっていってしまって元のスコープと全く変わっていってしまった」ような失敗事例のことを指して言っているのだが、説明としてはちょっと長くてわかりにくい。
このたとえ話を、欧米人に対して一言で、そのニュアンスを伝え切れるのでは、と思える方法を最近思いついた。
それは、こんな言い方。
「まるで第4回十字軍のようだ」
第4回十字軍。
エルサレムにいくはずが、その時々で「正しい」意思決定をしているうちにいつの間にかコンスタンティノープルに行ってしまった。目的を逸脱した十字軍だが、その当事者たちは「それでも自分達は正しかった」と主張していたに違いない。
エクスパットになるような欧米人なら、こんなストーリーをくどくど説明しなくても、この一言で言いたいことを理解するだろう。
まあ、そもそもこんな表現を必要とする事態に陥る状態になりたくないものだが・・・。


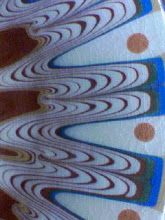

0 件のコメント:
コメントを投稿